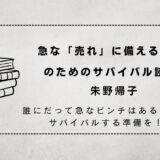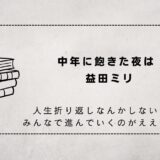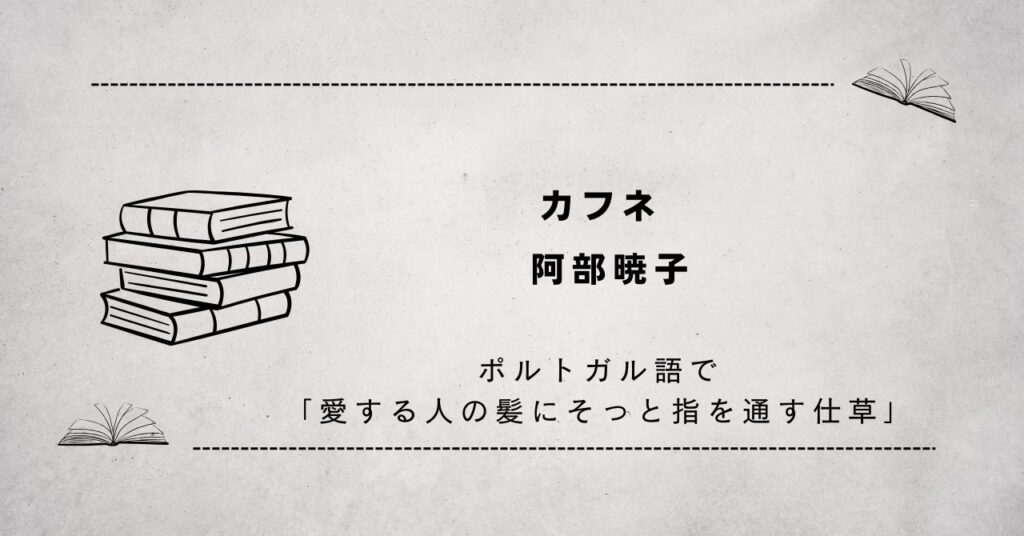
私の中で阿部暁子さんといえば「室町繚乱」。
ちょうど、本屋大賞の時に「カフネ」をみたけれど、そのときは「カラフル」を読んで・・・。
初めて読んだのが歴史の物語だったからか現代の物語への躊躇があったけど、御書印巡りをしていてばったり出会ったので「もうこれは読めということだ!」ということで、手に取ったのでした。
内容を見ないようにしていたから、表紙だけ見てもどんな内容なのか全然想像がつかない。でも、ちょっとだけ広告を見ていると、どうやら家事代行の話らしいと。
つまり、なんで読んだかは、阿部暁子さんが書かれていて、本屋大賞だったから、かな。
「だけど、私はそれだけでは心をたもてない」
仕事があって、家があって、いつか自分のもとに生まれてくる子のために貯めておいたお金もあって、きっとこれからも生きていくことはできる、その後に続く一言。
そう、最低限のモノがそろっていても人として心をたもって生きていけるかは人それぞれ。
私だって、夫の扶養で質素に暮らせば生きていける。それこそ、食料品の買い出しと娘の病院以外、一歩も外に出なくても暮らしていけるし、若干それを求められているようにも感じる。
家族や医師以外と話すことなく、家族の世話と家の用事だけをしているとどんどん「私には代えがある」「期限付きで使ってもらってる」という感覚になる。だから、家族と言われても私だけは入れ替え自由なパーツと思っていた時がある。
家族でいてほしいと、認めてほしいと、それを心の底から欲していた。そこにいていいって言ってほしかった。
それから数年、コロナ渦もあってオンラインでできることが増え、自宅にいてもいろんなことができるようになってきて、少しずつ外に目を向けられるようになってきた。子供たちを連れて、川の近くをうろうろしていたときはもう過去なんだ。
「さりげなく、気安く、手を貸せるようになる」
教育や福祉の中では、支援を受けるためにたくさんのハードルがある。それを乗り越えていける人だけが支援を受けられるのではないかと思えるような壁がある。申請主義なので当然なのかもしれないが・・・。
そうではなく、「切迫して困っている人をなるべくとりこぼさずに力になりたい」ということだと、グレーの人たちも受け入れた方がいい。そうすると困っている人もグレーの中に溶け込んで助けをもとめやすくなるから、と。
私が置かれているところとは違うけれど、でも、こんな風に考えてくれる人がいるかもしれない希望は嬉しい。制度ではなく、個人で、手の届く範囲の人で、自分ができる範囲のこと、そんなところからさりげなくできることをしていきたいと思えた。
大きくなくていい、大きくあろうとすると一歩踏み出せない。だから、できることをできる範囲で。
「カフネ」
ポルトガル語で「愛する人の髪にそっと指を通す仕草」らしい。
眠っている娘たちの髪をさわりながら、忙しすぎて心を失くしかけているような人たちが、こんな時間を持てるようにする仕事がしたいと思いました。
そういえば、無意識に娘の髪を触りながら祈っているときがある。娘が健やかでいられますように、明日も元気で活動できますようにって。
おわりに
外から見たら、サバサバ、テキパキ行動している人だからって、本当にそういう人かどうかはわからない。仮面や猫を上手にかぶっていることだってある。この本の登場人物だけでも、それぞれの人生があってそれぞれの痛みを持っている。
今、生活をしていても関わる人それぞれに人生があって、痛みを持っている。「多様性」という言葉なのかもしれないけれど、もっと身近な言葉にしてもいいんじゃないかな。
自分に語りかけるように相手にも語りかけられるように、そんな人にあこがれる。

イライラを持て余している人にぜひ。